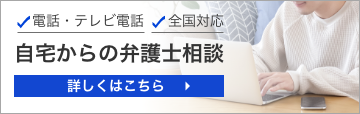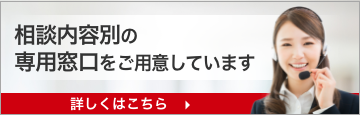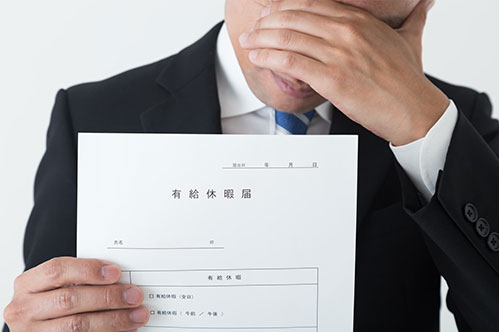セール期間延長は景品表示法違反? 割引キャンペーンの注意点
- 一般企業法務
- 景品表示法
- セール期間

神奈川県では、景品表示法に基づき、不当表示に対する行政指導が行われています。令和5年度の行政指導では、優良誤認表示や有利誤認表示に関する指導が計29件実施されました。
セールや割引キャンペーンなどを行う際、その期間や表示方法などは自由に決められるわけではありません。たとえば、セール期間やキャンペーン期間を繰り返し延長すると、景品表示法違反になるおそれがあるので十分ご注意ください。
本記事では、セールや割引キャンペーンなどを行う際に、景品表示法との関係で気を付けるべきポイントをベリーベスト法律事務所 横須賀オフィスの弁護士が解説します。
出典:「令和5年度行政指導の取組」(神奈川県)
1、景品表示法で禁止されている「有利誤認表示」とは
景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、事業者による不当な表示や過大な景品類の提供の規制をすることで、公正な競争を確保し、消費者が適正に商品やサービスを選択できる環境を整えることを目的としています。
景品表示法では、商品やサービスの価格などについて、一般消費者の誤解を招くおそれがある「有利誤認表示」を禁止しています。商品のセールや割引キャンペーンなどを企画する際には、この要件に該当しないように注意が必要です。
-
(1)有利誤認表示の要件
「有利誤認表示」とは、以下の①~③のすべてを満たす場合に該当します(景品表示法第5条第2号)。
- ① 事業者による表示であること
- ② 事業者が提供する商品またはサービスの価格その他の取引条件に関する表示であること
(例:商品の価格、割引率、ポイント還元率、支払条件、保証内容など) - ③ 以下のいずれかに該当する表示で、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあること
(a)実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
(b)競合他社のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
この「著しく有利」というのは、一般的な消費者が、その表示から受ける印象と実際の取引条件との間に重要な差があり、その差が消費者の選択に影響を与える程度であることを意味します。
また、表示を見た「一般的な消費者」が、実際よりも有利な取引条件だと誤解する可能性があることが条件です。専門的な知識を持った人だけが誤解するような表示は対象外となる可能性があります。 -
(2)有利誤認表示の具体例
以下のような表示は有利誤認表示に該当すると考えられます。
(例)
- 「今なら半額」と宣伝していたが、実際には常に「半額」の価格で販売していた。
- 通常価格を水増しして表示し、割引率を過大に見せていた。
- 「月額たったの1000円で利用可能」と称してサービスを契約させたが、実際にはさまざまな名目で追加費用がかかることになっていた。
- 「いつでも解約可能」と宣伝して商品の定期購入契約を勧誘したが、実際には解約するために厳しい条件が設けられていた。
これらの表示は、消費者庁から景品表示法違反と判断され、措置命令や課徴金納付命令の対象となる可能性があります。
2、セール期間や割引キャンペーンを設定する際の注意点
セール期間や割引キャンペーンに関しても、実施方法や表示方法が不適切である場合は、有利誤認表示に当たるおそれがあります。
セールや割引キャンペーンを行う事業者は、特に以下のポイントに注意し、適切な方法で実施することが重要です。
-
(1)セール期間やキャンペーン期間を何度も延長することは避ける
あらかじめ設定したセールやキャンペーンの期間を、繰り返し延長することは避けましょう。
期間を何度も延長すると、常にセール価格やキャンペーン価格で販売しているとみなされる可能性があります。
この場合、実際には割引をしていないのに、割引価格で商品を販売しているかのような印象を与えるものとして、有利誤認表示による景品表示法違反を指摘されかねません。
同じセールやキャンペーンは一度終了させ、一定の期間を空けて実施することが望ましいです。
キャンペーンを連続して実施したい場合は、企画の内容を変更することを検討しましょう。たとえば、先行するキャンペーンで割引を実施したなら、続くキャンペーンではノベルティのプレゼントやポイント還元を行うなどのアイデアが考えられます。 -
(2)販売実績が乏しい価格を「通常価格」と称してはいけない
実際には販売実績がほとんどない価格を「通常価格」と表示して、あたかも値引きされているかのように見せることは、景品表示法に違反する可能性があります。
「通常価格」として表示する価格(=比較対照価格)は、直近で一定期間にわたり販売実績のある価格とする必要があります。
全く販売実績がない価格や、かなり前の時期に販売実績があるにすぎない価格を「通常価格」とすることは避けましょう。
なお、セールやキャンペーンを実施することを決定した後に販売を開始した商品については、「通常価格」で販売していた期間があるとしても、実績作りを目的としたものにすぎないと判断されるおそれがあるので注意が必要です。
お問い合わせください。
3、セール・キャンペーンについて景品表示法違反を指摘された事例
セールやキャンペーンの広告表示が有利誤認表示に当たるとして、景品表示法違反を指摘された事例を紹介します。
出典:「景品表示法における違反事例集」(消費者庁)
-
(1)おせちを「50%OFF」と表示して販売した事例
事業者Aは、自社のウェブサイト上で、おせち料理について「通常価格(税込)21000円 割引率50%OFF 割引額10500円」と表示しました。
このような表示は、実際の販売価格が通常価格よりも安いという印象を一般消費者に与えるものです。
しかし、事業者Aが「通常価格」と称している価格は架空のものであり、その価格での販売実績がありませんでした。
そのため、事業者Aは、有利誤認表示によって消費者庁長官から措置命令を受けました。 -
(2)通信講座を「1万円引き」と表示して販売した事例
事業者Bは、自社のウェブサイト上で、資格取得に関する通信講座について「資格取得!応援キャンペーン」「全講座1万円割引実施中」「期間限定6月1日(日)⇒6月30日(月)まで」などと宣伝しました。
このような表示は、対象期間内に受講を申し込めば、正規受講料から1万円の値引きを受けられるという印象を一般消費者に与えるものです。
しかし、事業者Bはほとんどの期間において、正規受講料から1万円の値引きをするキャンペーンを実施しており、「期間限定」とする根拠がありませんでした。
そのため、事業者Bは、有利誤認表示によって消費者庁長官から措置命令を受けました。
4、景品表示法に違反した場合のペナルティー
景品表示法に違反する有利誤認表示を行った事業者は、消費者庁長官による措置命令や課徴金納付命令を受ける可能性があります。また、悪質な場合には刑事罰が科されるおそれもあります。
ここでは、景品表示法違反に対する主な処分や罰則について解説します。
-
(1)措置命令
有利誤認表示をした事業者は、消費者庁長官から措置命令を受けることがあります(景品表示法第7条)。措置命令の主な内容は、有利誤認表示の差し止めや再発防止措置などです。
措置命令を受けた場合、その内容や事業者名などが消費者庁ウェブサイトで公表されるため、企業の信用に大きな影響を与える可能性があります。 -
(2)課徴金納付命令
有利誤認表示を行った事業者に対しては、消費者庁長官から課徴金納付命令が出されることがあります(景品表示法第8条)。
課徴金の額は、有利誤認表示を行っていた期間(最長3年間)における、当該表示に係る商品や役務の売上額の3%相当額です。
ただし、課徴金の額が150万円未満の場合は、納付命令の対象外となります。 -
(3)刑事罰
令和6年10月以降、故意に有利誤認表示を行った事業者は、刑事罰の対象となる可能性があります。法定刑は「100万円以下の罰金」です(景品表示法第48条第2号)。
法人に対しても両罰規定によって「100万円以下の罰金」が科されます(同法第49条第1項第2号)。
また、以下の行為をした場合の法定刑は「1年以下の懲役または300万円以下の罰金」となります(同法第47条)。法人にも両罰規定によって「300万円以下の罰金」が適用されます(同法第49条第1項第2号)。- 消費者庁に求められた報告や物件の提出をしなかった場合
- 消費者庁に対して虚偽の報告をし、または虚偽の物件を提出した場合
- 消費者庁の検査を拒み、妨げ、または忌避した場合
- 消費者庁の質問に対して答弁をせず、または虚偽の答弁をした場合
さらに、消費者庁長官の措置命令に従わなかった場合の法定刑は「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」です(同法第46条第1項)。この場合、懲役と罰金の両方が科されることもあります(同法第46条第2項)。
法人にも両罰規定によって「3億円以下の罰金」が科されます(同法第49条第1項第1号)。
5、景品表示法に関するご相談は弁護士へ
商品やサービスについてセールスポイントや価格などの表示を行う際には、景品表示法の規制に注意しなければなりません。景品表示法の遵守を徹底するためには、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することには、主に以下のようなメリットがあります。
- 景品表示法に関する疑問点について、法的な観点から正しい回答を得られる
- 景品表示法によって禁止されている不当表示に該当しないように、表示の修正等についてアドバイスを受けられる
- 消費者庁から報告などを求められた際には、適切な対応ができるようにサポートを受けられる
景品表示法違反のリスクを最小限に抑えるためには、弁護士と顧問契約を締結して、日頃からアドバイスを受けられる体制にしておくと安心です。
6、まとめ
セールやキャンペーンを行う際には、景品表示法で禁止されている有利誤認表示に当たらないように注意しましょう。
セール期間やキャンペーン期間を何度も延長したり、販売実績がない価格を「通常価格」と称したりすると、有利誤認表示を指摘されるおそれがあります。
有利誤認表示のリスクを避けるためには、弁護士と顧問契約を締結して定期的にアドバイスを受けることをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所は、クライアント企業のニーズに応じて、リーズナブルにご利用いただける顧問弁護士サービスをご提供しております。
景品表示法に関するアドバイスを受けたい企業や、顧問弁護士をお探しの企業は、ベリーベスト法律事務所 横須賀オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|