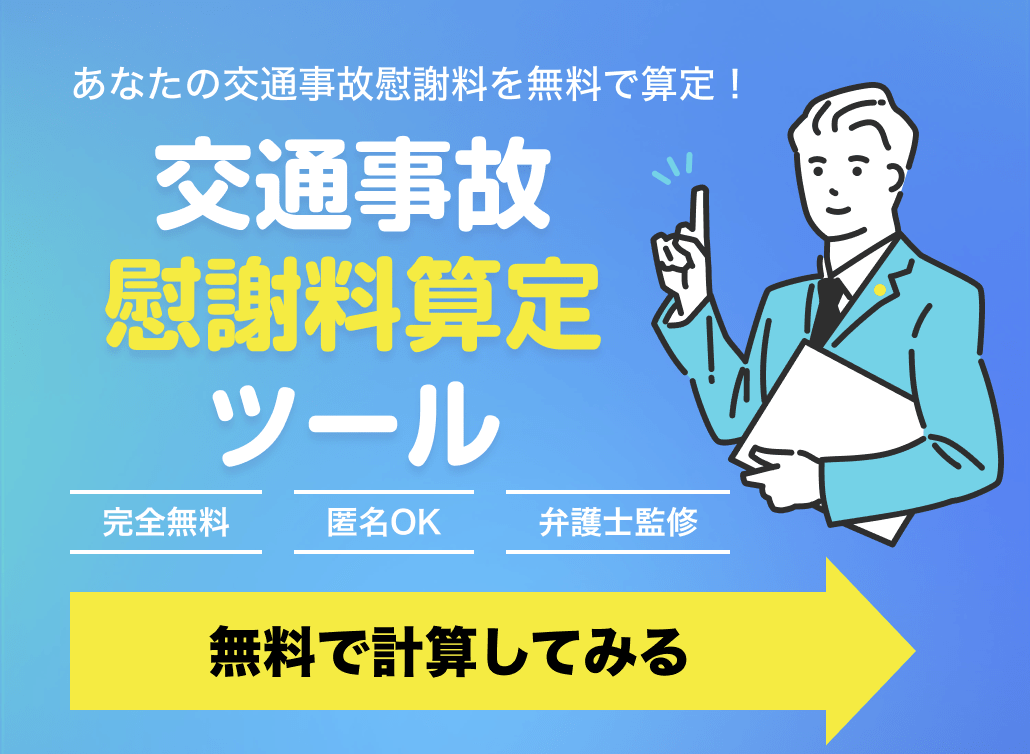交通事故で過失割合があると慰謝料はどうなる? 割合を変更するには
- 慰謝料・損害賠償
- 過失割合
- 慰謝料
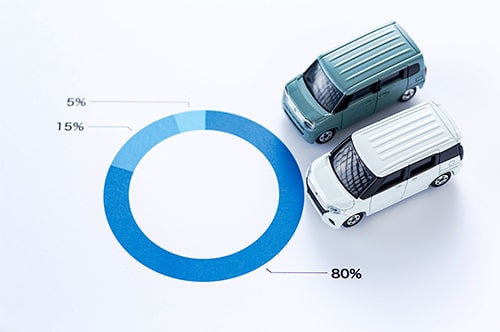
交通事故の被害に遭った際、相手方から提案された過失割合に納得できないと感じる方もいるでしょう。被害者にも過失があるとなれば、慰謝料を含む損害賠償金の受け取り額が減額されるおそれがあります。
しかし、保険会社から提示された過失割合が必ずしも適正であるとは限りません。事故の状況や証拠をもとに、過失割合を修正できるケースもあります。
本コラムでは、過失割合と慰謝料の関係や過失割合を変更する方法・慰謝料を増額するポイントなどについて、ベリーベスト法律事務所 横須賀オフィスの弁護士が解説します。


1、交通事故で過失割合がある場合の慰謝料│過失相殺とは?
交通事故の過失割合は、慰謝料を含む賠償金の額に影響します。被害者にも過失がある場合、その割合分を賠償金から減額する「過失相殺」という仕組みがあるためです。
以下では、過失割合や過失相殺がどのようなものか、また慰謝料に与える影響について解説します。
-
(1)過失割合とは|当事者双方の責任の程度
過失割合とは、交通事故における当事者それぞれの責任の程度を割合で示したものです。
たとえば、過失割合が「8対2(80対20)」である場合、加害者が80%・被害者が20%の責任を負うことを意味します。
この場合、被害者は、受けた被害のうちの80%については加害者から賠償を受けることができますが、残る20%については被害者自身が負担しなければなりません。
加えて、車同士の事故などでは、過失割合が大きい加害者の側にも何らかの被害が生じている場合があります。そのような場合、被害者は、加害者が受けた被害のうち、20%について賠償しなければなりません。
過失割合は、事故の状況や過去の裁判例などをもとに判断されます。まずは加害者側の保険会社から被害者に対して過失割合が提示され、交渉によって最終的に決定していくのが一般的です。
被害者自身で保険会社と交渉するには、提示された過失割合が適切なものかどうかを見極める必要があります。一度合意してしまうと、後日変更することは困難なので、慎重に判断しましょう。 -
(2)過失相殺とは|過失分を損害賠償金から減額
過失相殺とは、被害者にも過失がある場合に、過失の分だけ加害者が支払う損害賠償金を減らす仕組みです。
慰謝料だけではなく、治療費や通院交通費、休業損害などすべての損害賠償金が対象となり、減額されます。
たとえば、総額100万円の賠償金が認められても、被害者に20%の過失があると、受け取れる金額は80万円に減額されてしまいます。
交通事故では、停車中に衝突されたなどのもらい事故でない限り、被害者にもある程度の過失がつくのが一般的です。事故の被害者であったとしても、自らの不注意による過失分を加害者に請求することはできません。 -
(3)自賠責保険における過失割合の影響
自賠責保険は、被害者に対する最低限の補償を目的としているため、大きな過失がない限り、被害者の過失は損害賠償金に影響しません。
ただし、被害者の過失割合が70%以上ある場合には、以下のように受け取れる賠償金が減額されます。被害者の過失割合 減額される割合 傷害のみの場合 後遺障害または死亡した場合 70%未満 減額なし 減額なし 70%以上80%未満 20% 20% 80%以上90%未満 20% 30% 90%以上100%未満 20% 50% 表のとおり、減額の割合は、交通事故の被害が傷害のみの場合と、被害者に後遺障害が残ったり死亡したりした場合とで異なります。後遺障害とは、事故によるケガを治療しても完治せず、精神的・肉体的な障害が残った状態のことです。
なお、被害者側に100%の過失がある場合は、原則として自賠責保険からの補償は受けられません。
2、慰謝料金額の決め方と相場
以下では、交通事故の慰謝料の算定方法について、金額に影響する要素を解説していきます。また、算定する際に使われる基準や、算定基準別の慰謝料相場についても紹介します。
-
(1)慰謝料の金額に影響する要素
慰謝料は、以下の3種類に分類できます。交通事故で受けた被害によって、請求できる慰謝料は変わります。
慰謝料の種類 概要 入通院慰謝料 入院や通院することによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料 後遺障害慰謝料 ケガが後遺障害として認定された場合に、等級(1級~14級)に応じて支払われる慰謝料
※等級の数字が小さいほど重症死亡慰謝料 死亡した被害者と遺族の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料 これらの慰謝料の金額に影響するのは、主に以下のような要素です。
- 通院日数や入院日数
- 後遺障害の有無と認定された等級
- 怪我の程度
つまり、同じ「交通事故の被害者」であったとしても、状況に応じて慰謝料の金額には大きな差が出るということです。
-
(2)慰謝料の計算に使われる3つの基準
交通事故の慰謝料には3つの算定基準があり、どの基準で計算するかによって、慰謝料の金額が変わってきます。
慰謝料の算定基準 概要 自賠責基準 自賠責保険が定める最低限の補償額 任意保険基準 加害者側の任意保険会社が独自に定めている基準 弁護士基準(裁判基準) 弁護士や裁判所が使用する過去の裁判例にもとづいた基準 このうち、もっとも低い慰謝料となるのが自賠責基準、もっとも高い慰謝料となるのが弁護士基準です。
任意保険基準は、保険会社によって異なりますが、自賠責基準と同等かやや高い程度であることが一般的とされます。 -
(3)基準ごとの慰謝料相場
慰謝料の金額は、事故の状況や入通院日数・後遺障害の有無・算定基準などによって大きく異なります。
たとえば、むち打ちで治療期間が6か月間・入院日数が0日、通院日数が週2日程度(48日程度)であった場合の入通院慰謝料の相場は、以下のとおりです。なお、任意保険基準の相場は保険会社により異なり、その内容も一般には非公開とされています。慰謝料の算定基準 入通院慰謝料の相場 自賠責基準 41万2800円 弁護士基準(赤い本基準) 89万円 上記のとおり、自賠責基準と比べると、弁護士基準は相場の金額が2倍程度大きくなっています。
ただし、慰謝料の金額は、過失割合や個別の事故状況などによって調整される可能性があります。必ずしも相場と同じ金額が受け取れるとは限らないため、注意が必要です。
お問い合わせください。
3、過失割合に納得できない場合の対策
先述のとおり、交通事故の過失割合は、まず加害者側の保険会社から提示されます。その過失割合に納得できない場合、交渉によって変更できる可能性があります。交渉するには、適正な過失割合を判断する方法を確認し、弁護士へ相談することを検討しましょう。
-
(1)過失割合の適正な判断方法
適正な過失割合を判断するためには、まず事故状況を確定し、どの事故類型に該当するかを確認する必要があります。
事故類型とは、交通事故を当事者の種類(自動車・バイク・自転車など)や事故時の行動によって分類したものです。
完全に一致する事故類型がなかった場合は、類似した事故類型を参考に基準となる過失割合を決定します。基準の過失割合が決定したら、一時停止やウィンカー、速度違反の有無など個別の事情を考慮し、過失割合に修正を加えます。
過失割合の適正な判断には、「事故状況を客観的に示す証拠」と「過去の判例や事故類型に関する知識」が必要です。 -
(2)弁護士に相談することで過失割合を変更できる可能性がある
弁護士は、保険会社から提示された過失割合が適正かどうかを法的な観点から検証します。また、被害者に代わって保険会社との交渉を行うことも可能です。
そのため、被害者により有利な過失割合に変更できる可能性があります。過失割合が変更されれば、過失相殺される割合も減り、受け取れる慰謝料の増額も見込めるでしょう。
「提示された内容に納得がいかない」と感じたときは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
4、過失がある場合に慰謝料を最大限もらうためにできること
自分に過失がある交通事故でも、対応次第で慰謝料の金額を引き上げられる可能性があります。以下では、交通事故の被害者ができる具体的な行動や注意点を確認していきましょう。
-
(1)事故状況を確認し証拠を確保する
まずは事故状況を確認し、できるだけ多くの情報を収集しておくことが大切です。
事故状況を正しく記録しておくことで、過失割合の交渉や慰謝料請求で役立ちます。
主な証拠として挙げられるのは、以下のようなものです。- 事故直後の現場や車両の破損状況の写真
- 相手車両や運転者の情報
- ドライブレコーダーの映像
- 当時の天候や交通状況のメモ
- 目撃者の証言
- 事故現場付近の防犯カメラ映像
中でも、ドライブレコーダーの映像は重要な証拠になりますが、レコーダー内の映像が上書き保存されて消えてしまう事態がしばしばみられます。
そのため、自身や相手の車にドライブレコーダーがついていても安心せず、事故直後のうちに記録されている映像を別の媒体に移して保存するなど、しっかりと証拠を保全しておく必要があります。
これらをもとに事故の客観的な状況を立証できれば、保険会社との交渉を進めやすくなるでしょう。 -
(2)実況見分調書を活用する
自身で事故状況を記録するほか、警察が作成する「実況見分調書」を活用することも大切です。
実況見分調書とは、事故後に警察が現場で調査した内容をまとめた文書です。事故の発生状況・道路や車両の状況・運転者の証言・事故現場の写真(見取り図)などが記録されています。
ケガで病院に直行するなどしない限りは、警察到着後の聞き取り調査にできるだけ協力して誠実に対応するようにしましょう。実況見分調書が正しく作成されることで、保険会社から提示された過失割合と実際の状況にズレがないかをチェックできます。 -
(3)交通事故後の対応で注意すべきポイント
交通事故に遭ったあとは、被害者として不利になる行動を避けることも重要となります。具体的には、以下のような行動に注意が必要です。
- 警察に届け出ない
- 目撃者の連絡先を確認しない
- 加害者とその場で示談を成立させる
交通事故が発生した際は、軽微な事故であったとしても必ず警察に通報する必要があります。目撃者がいる場合は、証言が証拠となる可能性があるため、忘れずに連絡先を確認しておきましょう。
また、加害者からその場で示談金を支払うと言われたとしても、応じる必要はありません。被害に応じた適切な慰謝料を請求するためにも、事故直後の示談は避け、保険会社などを介して交渉するようにしましょう。
これらのポイントを意識して冷静に行動することで、結果的に慰謝料の増額につながりやすくなります。 -
(4)弁護士基準での請求による慰謝料増額
慰謝料を最大限に受け取るためには、弁護士基準による請求が望ましいです。
先述のとおり、弁護士基準は過去の裁判例にもとづいた基準で、自賠責基準や任意保険基準よりも損害賠償金が高額になる傾向があります。
ただし、弁護士を入れずに被害者自身で交渉をし、弁護士基準の慰謝料を請求するのは困難です。そのため、慰謝料を増額したい場合には、まず弁護士に相談するようにしましょう。
5、まとめ
自分自身にも過失がある交通事故であっても、正しく対応すれば適正な慰謝料を請求できます。重要なのは、事故の状況を正確に把握し、証拠にもとづいて交渉を行うことです。
保険会社との交渉に不安がある方は、弁護士への相談をおすすめします。弁護士に相談することで、過失割合の見直しや慰謝料の増額といった納得のいく結果を得られる可能性が高まります。
交通事故の過失割合や慰謝料請求で悩んだときは、ぜひベリーベスト法律事務所 横須賀オフィスの弁護士にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています